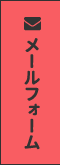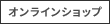メンタルヘルスの常識の一つに「うつ病患者を励ましてはいけない」というのがあります。
今では多くの人が認識していることですが、実はこの常識。専門家たちに言わせてみれば間違っているようです。
正確には、この言葉の持つ意味が間違って解釈されたまま独り歩きしているということらしい。
「うつ病患者を励ましてはいけない」 の真意は、元々は「むやみに叱咤激励するものではない」という意味だったというわけなんですよ。

うつ病患者は真面目で責任感のある人が多く、自分自身を責めたり自分を追い詰めてきているような状態なので、そこへ「もっとしっかり頑張れよ」「元気出して!」という叱咤激励の意味を込めた言葉をかけるのはさらに追い詰めることになり逆効果です。
「もうこれ以上頑張れない」あるいは「元気を出したいけど出せない」というのがうつ病だからです。
そのような場合には「無理せずに休めばいいよ」「大丈夫ですよ」というような負担を軽くしたり安心させるような励まし方をするのが望ましいとされています。
つまり本来は「励ましてはいけない」のではなくて「叱咤激励するような励まし方がいけない」という意味だったものが、一律に「励ましてはいけない」という風に誤解されて認識されるようになったということなんですね。
・・・ということで「うつ病患者は励ましてはいけない」というのは半分は本当で、半分は間違いだったということが言えるかと思います。
ただし・・・ただしですよ。うつ病患者といっても症状の程度には個人差があったり、症状のタイプに違いがあったりと人によって様々です。
「無理せずに休めばいいよ」「大丈夫ですよ」というような言葉でさえも、場合によっては「ああ、気を遣わせてしまったな」と悪く捉えてしまうこともあるのがうつ病の複雑なところです。
これは、言葉そのものに意識がいっているわけではなくて、言葉がけをしてくる人の気持ちに意識がいっているからであり、自分がどう思われているかが敏感なまでに気になり、かけてもらった言葉の真意を感じ取ってしまうようです。
いくら優しい言葉をかけたとしても、その言葉の裏に隠された「なんとかしてあげたい」という気持ちを感じ取ってしまい、「ああ、気を遣わせてしまったな」と負担に感じてしまうこともあるということです。
このような場合は、無理になんとかしてあげようとせずに、そっとしておいてあげることも方法の一つのようです。
といっても放っておくのではなく、温かく見守ってあげるということ。
傍にいて、決して「独りではない」という状況を作り、相手が何かを求めてきた時には話を聞いて共感してあげることが大事なようです。
なにか上手な言葉をかけられなくてもいいんです。言葉よりも寄り添う。
それが何よりも大切なのではないでしょうか。