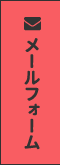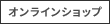風呂に浸かっていると長風呂しなくてもすぐにのぼせてしまう人がいますよね。
当館でも時々、浴場でのぼせられて気分が悪くなるお客様がいらっしゃいます。
主な症状は吐き気、めまい、ふらつき、失神など。
こんな場合は浴槽や浴室から出して寝かせるか、できるだけ頭を低くするような態勢をとらせます。
基本的には熱中症の対応と同じように冷たいタオルで頭を冷やし、体表面も熱くなっている場合は涼しませるようにします。
基本的には熱中症の対応と同じように冷たいタオルで頭を冷やし、体表面も熱くなっている場合は涼しませるようにします。
このとき気になるのは血圧です。
それはたまたまの「のぼせ」なのか。その裏に何か重大な病が隠れていることもあるからです。
状況によっては救急車を呼ばせて頂くこともあります。
状況によっては救急車を呼ばせて頂くこともあります。

そもそも入浴でのぼせるのは脳がオーバーヒートを起こした場合です。
ヒトは熱すぎても冷たすぎても緊張やストレスを感じるので交感神経が刺激されます(暑さ寒さにおいても)
※ここ理解するうえで結構大事なポイント(ちょっと話が脱線しますよ)
交感神経と副交感神経は相対関係にあるため、「ぬるい温度は副交感神経が刺激され血管が拡張され血流が良くなるので頭がのぼせる」と考えがちですが副交感神経によって血管が拡張することはありません。
血管を支配しているのは交感神経のみです。
副交感神経の働きが促進されると、血管内皮細胞から遊離されるNO(一酸化窒素)によって血管が拡張しますので「副交感神経が血管を拡張させる」というのはあながち間違いでもありませんが、直接働きかけているわけではありません。
だから血圧を下げるには、副交感神経の働きを促進させる薬ではなく、交感神経の働きを遮断する薬を用いることで血管を拡張させます。(ただし、副交感神経作動薬は他の治療目的で使用した場合に副作用の結果として血管が拡張される場合はある)
しかも交感神経刺激に対する血管の反応は部位によって収縮ばかりとは限らず
・血管収縮・・・皮膚、粘膜、腹部内臓、脳の血管
・血管拡張・・・心臓の冠動脈、肺、骨格筋の血管
となっています。
お風呂に浸かると脳内の血流が増加するのは、血管が拡張されるからではなく、熱を放散しようとする体温調節機能によるためです。
交感神経と副交感神経は相対関係にあるため、「ぬるい温度は副交感神経が刺激され血管が拡張され血流が良くなるので頭がのぼせる」と考えがちですが副交感神経によって血管が拡張することはありません。
血管を支配しているのは交感神経のみです。
副交感神経の働きが促進されると、血管内皮細胞から遊離されるNO(一酸化窒素)によって血管が拡張しますので「副交感神経が血管を拡張させる」というのはあながち間違いでもありませんが、直接働きかけているわけではありません。
だから血圧を下げるには、副交感神経の働きを促進させる薬ではなく、交感神経の働きを遮断する薬を用いることで血管を拡張させます。(ただし、副交感神経作動薬は他の治療目的で使用した場合に副作用の結果として血管が拡張される場合はある)
しかも交感神経刺激に対する血管の反応は部位によって収縮ばかりとは限らず
・血管収縮・・・皮膚、粘膜、腹部内臓、脳の血管
・血管拡張・・・心臓の冠動脈、肺、骨格筋の血管
となっています。
お風呂に浸かると脳内の血流が増加するのは、血管が拡張されるからではなく、熱を放散しようとする体温調節機能によるためです。
さて、話を戻して・・・
熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、心臓がバクバクし血圧が上がります。
体温の上昇を防ぐために、熱を外に逃がさなければなりません。
しかしヒトには体温を下げる方法は発汗しかありません。
そのため血流が促進されます。
体温の上昇を防ぐために、熱を外に逃がさなければなりません。
しかしヒトには体温を下げる方法は発汗しかありません。
そのため血流が促進されます。
交感神経が刺激されると心臓を頑張らせる働きがあります。
つまり心拍数と拍出量の増加です。これによって血流が促進されます。
つまり心拍数と拍出量の増加です。これによって血流が促進されます。
熱の放散(発汗)は体全体で行われていますが、血流は頭部にも集まりやすくなります。
脳血管には脳内の血流を調節する自動調節機能があるので、通常は脳循環は一定に保たれています。
脳は生命にとって大事な部位なので特別機能があるようです。
脳は生命にとって大事な部位なので特別機能があるようです。
しかし発汗が追い付かず熱を発散できなければオーバーヒート状態となり、脳細胞は正常に機能できなくなり吐き気や失神といったのぼせ症状を引き起こします。
これは熱中症と同じこと。
これは熱中症と同じこと。
正常な人ですら血圧が上がるのですから、血圧の高い人はさらに注意が必要です。
高血圧症の人の血圧がさらに高くなると、血管の中のかさぶたが血流に乗って細い血管で詰まれば脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすことになります。また高血圧は脳出血の原因にもなります。
高血圧症の人の血圧がさらに高くなると、血管の中のかさぶたが血流に乗って細い血管で詰まれば脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすことになります。また高血圧は脳出血の原因にもなります。
そんなわけで、高い温度は「のぼせ」の直接的な原因となります。
一方、
熱くない温度でも「のぼせ」は起こりえます。
それは長湯をした場合。
長湯の問題点は体力を消耗することと脱水しやすいことではありますが、のぼせの原因にもなることです。
これは体が温まり、血流が増加することで起こります。
熱くないのであれば交感神経によって血管が収縮することはありません。
よって血圧が高くなるわけではないので、血流が良くなります。
熱くないのであれば交感神経によって血管が収縮することはありません。
よって血圧が高くなるわけではないので、血流が良くなります。
熱くなくても頭に血が上った状態が続けばオーバーヒート状態となり、そのうち顔が火照ったりボーっとしてきます。
それがのぼせ。
それがのぼせ。
もし長湯でなくぬるいお湯でものぼせてしまうという人は特に要注意です。
ぬるいお湯に浸かった場合は交感神経ではなく副交感神経が優位になるので、血管が収縮することはなく血圧は上がらないはずです。それなのにのぼせるということは、熱が発散できないほど血流が悪いということです。
これは動脈硬化がある可能性も考えられます。
1.入浴前にコップ1杯の水を飲む
入浴で発汗すると血液の水分量が減るので血液に熱を籠りやすくなってしまいます。
それ以上に脱水症状を予防するという意味でもコップ1杯の水分補給はしておきたいところです。
それ以上に脱水症状を予防するという意味でもコップ1杯の水分補給はしておきたいところです。
2.かけ湯をする
入浴前にかけ湯をするのは清潔のためではありません。
温度に慣らしたり急激な血圧の変化を予防するという意味があります。
温度に慣らしたり急激な血圧の変化を予防するという意味があります。
3.ぬるめのお湯で半身浴
のぼせの1番の原因は言うまでもなく高い温度。
40℃以下のお湯で全身浴よりのぼせにくい半身浴が良いでしょう。
40℃以下のお湯で全身浴よりのぼせにくい半身浴が良いでしょう。
4.頭にタオルを乗せる
頭寒足熱といって頭は涼しい方が良い。
冷たいタオルを頭の上に乗せて熱から脳を守りましょう。
風邪をひいて発熱したときにおでこに冷たいタオルを当てるのと同じです。あれは熱を下げるためではなく、熱から脳を守るためなんですよ。
冷たいタオルを頭の上に乗せて熱から脳を守りましょう。
風邪をひいて発熱したときにおでこに冷たいタオルを当てるのと同じです。あれは熱を下げるためではなく、熱から脳を守るためなんですよ。
5.立ち上がる時はゆっくりと
浸かっていた湯船から出るときはゆっくりと立ち上がりましょう。
クラっと立ちくらみを起こす場合がありますが、あれは起立性低血圧といってのぼせとはまた違う症状なんですよ。
クラっと立ちくらみを起こす場合がありますが、あれは起立性低血圧といってのぼせとはまた違う症状なんですよ。
なお、以上のことから、のぼせやすい体質には高血圧が該当しますが、冷え性も考えられます。
冷え性とのぼせは対極の関係にあるようにみえますが、冷え性とのぼせには体温調節ができない症状であるという共通点があります。
冷え性かつのぼせやすい人は、まず冷え性を改善することを考えましょう。